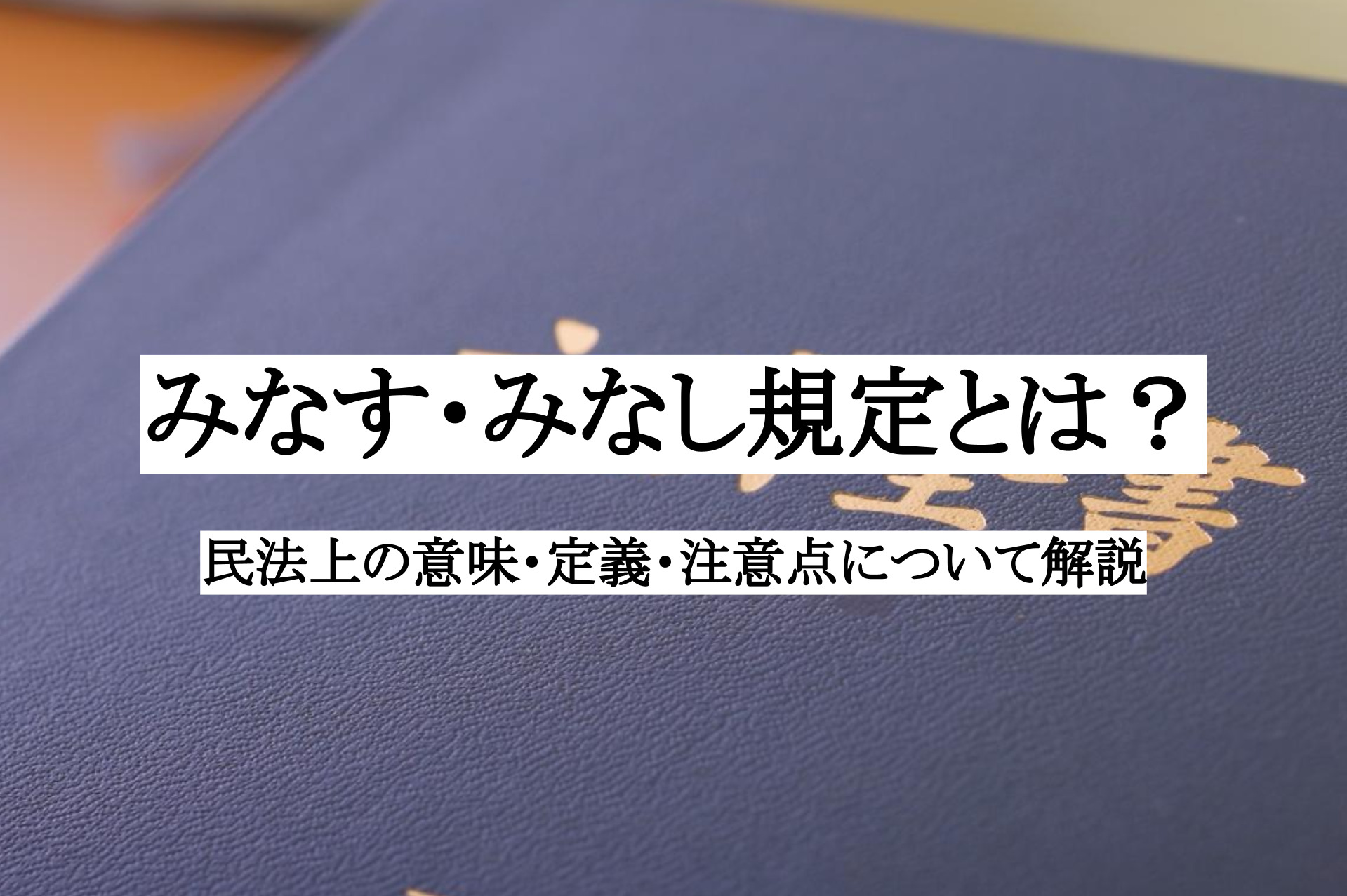
【意味・定義】みなすとは?
みなすとは、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認めることをいう。このため、たとえその事実とはことなる反証があったとしても、認められない。
【意味・定義】みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める規定のことをいう。
【意味・定義】みなす・みなし規定とは?
みなす=当然にそのように扱われる
「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。
このような効果を持つ制度を「擬制」といいます。
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。
みなす=反証が認められない
「みなす」は、たとえ反証があった場合であっても、その反証は認められません。
逆にいえば、反証を認めるべきでない規定で、「みなす」という表現が使われています。
この点が、反証が認められる「推定する」(「推定規定」)とは異なります。
【意味・定義】推定規定とは?
推定規定とは、「推定する」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、反証がない限り、法律上、そのような効果を認める規定のことをいう。
みなし規定に関する補足
民法では、次の規定がみなし規定です(随時更新)。
いずれも、実態や当事者の真意よりも、法的な安定性を優先することを目的としている規定です。
ただし、第125条(法定追認)に限っては、当事者の意思(意義をとどめること)により、異なる効果を発生させる事ができるため、特殊な例外といえます。
契約実務における注意点
みなし規定≒強行規定
すでに述べたとおり、みなし規定は反証が認められない規定です。
わざわざ法律でそのように決めている以上、みなし規定は、すべてが強行規定であるものと思われます。
このため、契約においてみなし規定を否定するような規定があったとしても無効となる可能性が高いといえます。
みなすは契約文章でも使われる
なお、「みなす」という表現は、契約書を起案する際にも使用します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】検査に関する条項
第○条(検査)
1 受託者からの製品の納入があった場合、委託者は、当該納入があった日から起算して10日後まで(以下、「検査期間」という。)に、当該製品についての検査をおこない、かつ当該検査の合否について、受託者に対し通知するものとする。
2 前項にかかわらず、検査期間の経過までに受託者に対する前項の通知がなかった場合、前項の製品は、検査に合格したものとみなす。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
上記の例では、検査期間が経過した場合は、製品は検査に合格したものと扱われます。
この場合、仮に製品の中に不合格品があったとしても、反証は認められないことになります。
このため、契約交渉の際に優位な立場にある場合、自分にとって不利となる内容に関しては、推定規定に変更することも検討します。
みなす・みなし規定に関するよくある質問
- みなすとは何ですか?
- みなすとは、みなすとは、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認めることことです。
- みなし規定とは何ですか?
- みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことです。