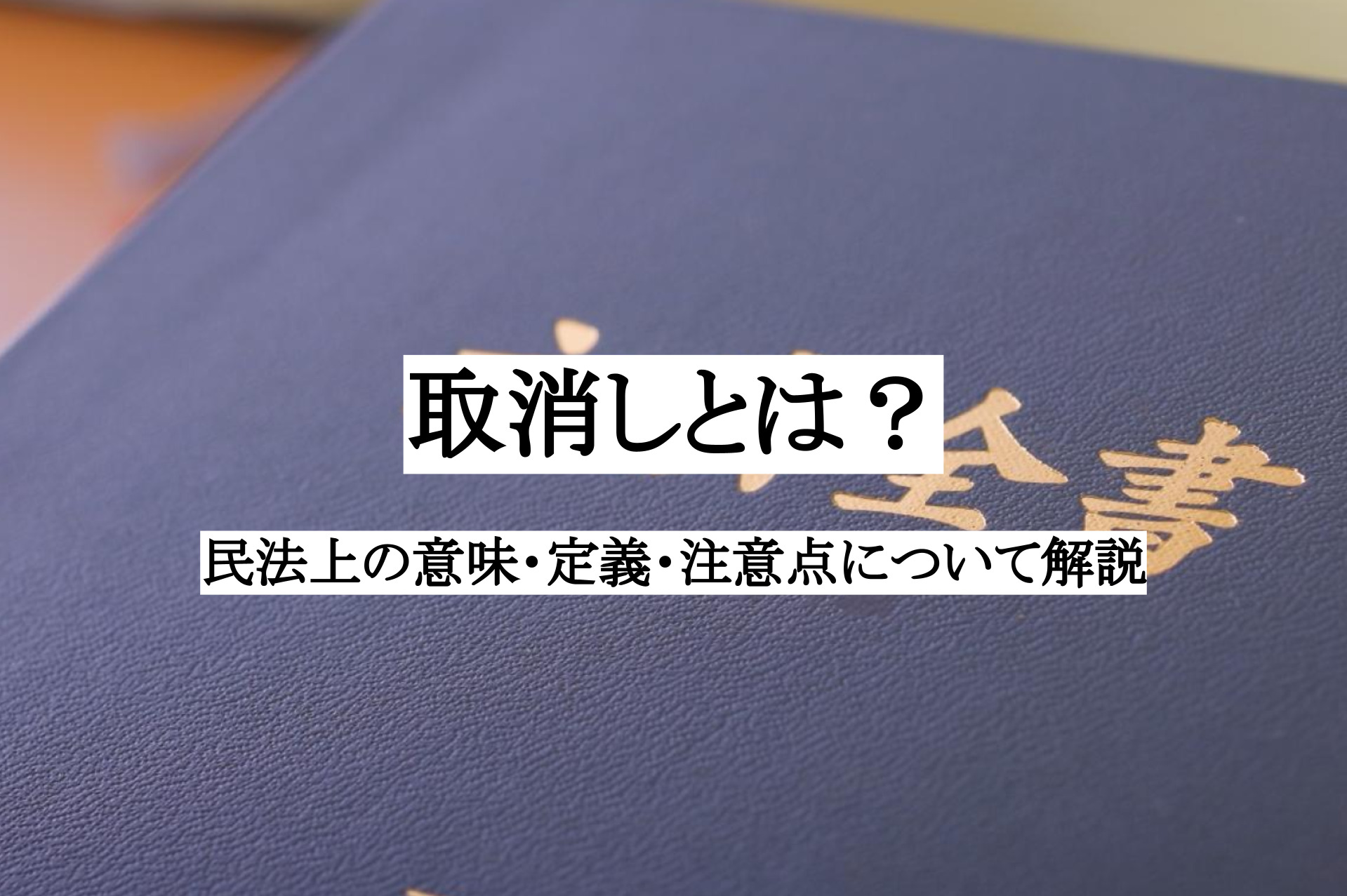
【意味・定義】取消しとは?
取消しとは、いったん有効に効果が生じた法律行為を遡って無効にすることです(ただし、これはあくまで法律行為の取消しの場合に限ります)。
民法において、取消しができる法律行為は、いったんは完全に効果が生じます。
また、後で取消すことで、無効にすることもできます(第121条参照)。
さらに、取消しができなくするために追認することもできます(第122条参照)。
この点は、最初から完全に効力を生じることはなく、追認することもできない無効な行為とは大きく異なります(第119条参照)。
取消しうべき行為とは?
取消しうべき行為とは、取り消すことのできる行為のことで、具体例としては、以下のものがあります。
取消しうべき行為=取り消すことのできる行為
- 制限行為能力者が単独でおこなった法律行為
- 錯誤、詐欺または強迫にもとづく意思表示(瑕疵ある意思表示)
取消権者とは?
取消権者とは、取消しができる者のことです。
制限行為能力者の行為の取消権者
制限行為能力者行為にあっては、主に次の者をいいます(民法第120条第1項)。
取消権者(制限行為能力者による法律行為)
- 制限行為能力者本人(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)
- 制限行為能力者の代理人(親権者、未成年後見人)
- 制限行為能力者の承継人
- 同意をすることができる者(成年後見人、保佐人、補助人等)
錯誤、詐欺または強迫=瑕疵ある意思表示の取消権者
錯誤、詐欺または強迫(瑕疵ある意思表示)にあっては、主に次の者をいいます(民法第120条第2項)。
取消権者(瑕疵ある意思表示)
- 瑕疵ある意思表示をした者
- 瑕疵ある意思表示をした者の代理人
- 瑕疵ある意思表示をした者の承継人
取り消された法律行為はみなし無効
取消しがあった法律行為は、最初から無効であるものとみなされます(いわゆる「みなし規定」)。
【意味・定義】みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める規定のことをいう。
このため、取消されるまでの間、取消しができた法律行為を前提として、更に行為を重ねていった場合に、(特に第三者との間で)後の行為の有効性や利害の調整を巡ってトラブルになることがあります。
この点については、取消しの原因によって取扱いが異なりますので、個々の状況ごとに判断する必要があります。
取消しと無効の違いとは?
取消しに似た制度に、無効があります。
取消しは、いったんは効果が生じるものであるのに対し、無効は、最初から効果を生じません。
このため、取消しと無効の違いは、効果が生じた後で効果が無くなるのか、または最初から効果が生じないのか、という点にあります。
取消しと無効の違い
取消しは、いったんは効果が生じた後に、取消権者から取り消されることによって過去に遡って無効となるのに対し、無効は、最初から効果を生じない。
契約実務における注意点
契約実務では、相手方が取消しできる契約は、不安定な契約であるといえます。
このため、民法に規定する方法(催告など。第20条第4項・第20条第3項・第20条第4項参照。なお、同様の趣旨で第114条参照。)で、
相手方による取消し、または追認を明らかにして、取消しを受けるか、取消される可能性のない契約とするべきです。
特に、制限行為能力者との契約の場合は、取消しの後の契約の清算により、思わぬ損害が出てしまう可能性があります。
この点は、特に注意が必要です(いわゆる「現存利益」について、第121条の2第2項参照)。
取消しに関するよくある質問
- 取消しとは何ですか?
- 取消しとは、いったん有効に効果が生じた法律行為を遡って無効にすることのことです。
- 取消しと無効の違いは何ですか?
- 取消しは、いったんは効果が生じた後に、取消権者から取り消されることによって過去に遡って無効となるのに対し、無効は、最初から効果を生じません。